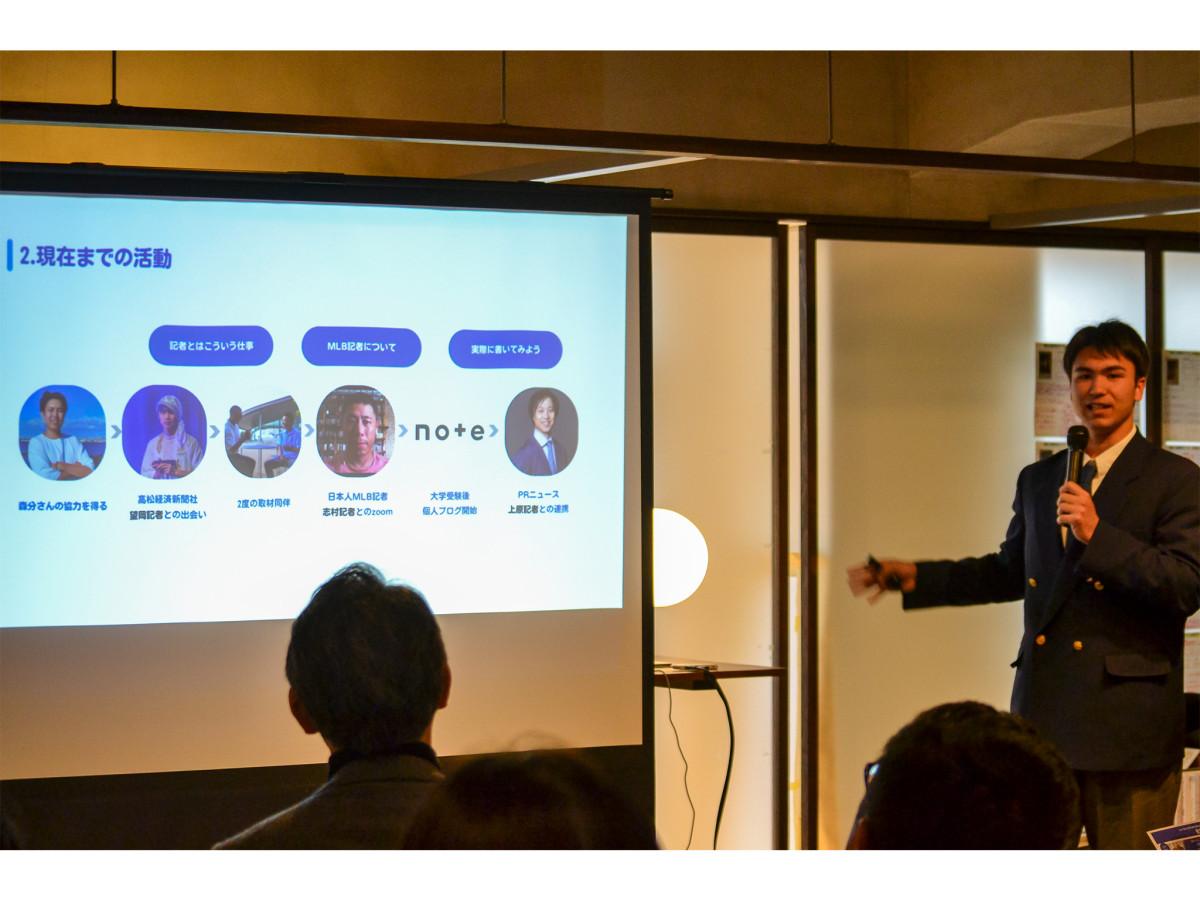【高松を元気にする100人 VOL.3】田中未知子さん【瀬戸内を現代サーカスの聖地に】
高松を元気にする100人 VOL.3 瀬戸内サーカスファクトリー 田中未知子さん
1970年代にフランスで産声を上げ、今や世界的な広まりを見せる「現代サーカス」。演劇、ダンス、映像、音楽とあらゆるアートを組み込みながら、身体動作の可能性を追求した極限世界のパフォーマンスは、もはや体の持つ力を忘れかけた現代人の心を打ち震わせる。
田中未知子さんは、そんな現代サーカスの魅力を日本から発信する唯一無二のイノベーターだ。フランス取材、専門書の出版、地方国際芸術祭への参加など精力的な普及活動の末、香川県を拠点に創作団体「瀬戸内サーカスファクトリー」を設立した。
ある時は工場で、またある時は図書館で、鉄工所で、歴史的建築の中で、田中さんは自由に創造力の翼を広げ、常識にとらわれない作品を生み出し続けている。
活動の目的は一貫して「地域とともに文化を作り、育てること」。10年以上に及ぶ芸術活動の軌跡、その先に思い描く文化の未来について語ってもらった。
一般社団法人「瀬戸内サーカスファクトリー」の代表理事であり、現代サーカスディレクターでもある田中未知子さん
-小さい頃からサーカスに興味があったのですか。
それが全然なくて。小さい時にキグレサーカスという、木下サーカスよりもちょっと小さいぐらいのサーカスは見たことがあったんですけど、その時もあまり感動はせず…。サーカスには本当になじみがなかったです。
現代サーカスと出合ったのは2004(平成16)年。私は北海道の出身で、元々北海道新聞社の事業局に勤めていたんですが、たまたまその頃に札幌市の財団が新聞社と組んで、「新しい劇場のこけら落としとして何か変わったものをできないか」という話をしていた時にフランスの現代サーカスを呼ぶことになったんです。
私は現代サーカスを全く知らなかったんですが、見たこともないような世界にすごく引かれまして。学生時代に1年間留学していて、フランス語がしゃべれるということもあってフランスとの窓口をやらせてもらうことになりました。フランスからはサーカスアーティストが13人ぐらい来たのですが、初めて彼らが部屋に入ってきた瞬間に、世界が崩れ落ちるぐらいの衝撃を覚えたのを今でもよく覚えています。
-見た目のインパクトがあったということですか。
アーティストの、目ですね。見たことがないような目っていうのかな…。大抵の人は、やっぱり社会の中での自分のポジションであるとか、職業によって知らず知らずのうちに、人を上に見たり、下に見たりするものだと思うんですけど、それが全くなくて…。もう真っすぐな、上でもなければ下でもない、本当に同じ視線の人たちばっかりだったんです。
温かい、優しい視線で。「13人そろって、どうしてみんなこんな目なんだ」「何なんだろう、この人たちは」って思いました。サーカスというより、サーカスを生きている人たちの目に衝撃を受けたんですよね。
-その後、新聞社を退職し、現代サーカスの本を出すと決めてフランスに渡ったそうですが、フランスではどういう生活を送っていたんですか。
フランスにずっと住んでいたわけではないんです。3カ月ぐらいフランスに行って取材して、日本に戻って3カ月ぐらいたったらまたフランスに行ってという風に、日本とフランスを行き来していました。
ほれ込んでいるといっても、最初は全然現代サーカスの世界を知らないし、全く知らない世界に飛び込むような感じ。ただ、パリにあるフランス国立のサーカス情報センターの場所は知っていたので、所長に直談判して「3カ月間、私を受け入れてください」って言いました。普通だったらそんなことはあり得ないんですが、センターの所長は何か意義を感じたのか「いいよ」と言ってくれたんですよね。
でも所長がトップダウンで言ったことなので、現場は「そんなこと聞いてない」みたいな。初日にすごくドキドキして行ったら「君の席はない」なんて言われたんですけど、「もう日本に戻れないから、お願いだから席をくれ」と言って、結局1カ月いさせてもらいました。
-すごいですね。
ふふふ。でも実際はその事務所にずっといたわけじゃなくて、私は本を書くためにほとんど出掛けていて。サーカス学校を訪ねたりフェスティバルを訪ねたり、とにかく旅をしていろんな人に会うという連続でした。
情報センターにはもちろん情報がたくさんあるんですが、フランスの現代サーカスは昔からのサーカスと違って、芸術学校で習ってプロになっていくものなので。
-学校があるんですね。
少なくとも500校はありますね。フランスはとにかく現代サーカスが身近な国なんですけど、サーカスをやりたいと思った人がどうやって学んで、どういうルートでプロになって、その後どんな風に活動するのか、どうやって生きていくのか、そういう情報も日本には全くなかったんです。
なので向こうに行ってからいろんなところに入り込んで状況を聞いて、現代サーカスがどういう構造で成り立っているかを理解するために1年ぐらい駆けずり回っていたという感じです。
チュニジアの国立サーカス学校も来訪
その後は日本に帰って、半年ぐらい執筆活動に専念しました。一応出版社は決まっていたんですけど、実際に本を出してくれると決まるまでがすごく長くて、結局始めてから出版まで2年半かかりましたね。
-形になった本を見た時はどうでしたか。
何て言うんだろう、本当なのかなって。1年間、全てを捧げて書いたものがこの世に出ないかもしれないということで、1年半待っていたので…。もう永遠かと思うぐらい長かったので、本が出た時は信じられないというか、しばらくは現実と思えませんでした。
本屋さんに置かれ始めた後は、新聞で書評に取り上げていただいたり、東京の丸の内の本屋さんでもPOPを立てて置いていただいたりして、本当にうれしかったです。生まれて初めての、人生を賭けたチャレンジだったので…。
本が出たことで、本が語ってくれることが多くなったというか、それまでは自分がしゃべった範囲の人しか知らなかったことを、多くの人が知ってくれるようになりましたね。自分の知らないところで、私のことや本のことを知っている人が現れて「現代サーカスのこと、こんな風に書かれていましたね」と言ってくれるようになりました。
-本の出版後は香川県を普及活動の拠点にされていますが、香川県を選ばれた理由は何でしょうか。
北海道出身なので、西の方は全然知らなかったんですけれども、2010(平成22)年に開かれた第1回瀬戸内国際芸術祭のパフォーミングアーツを担当することになって、初めて瀬戸内、香川県を訪れました。
香川には農村歌舞伎や獅子舞、人形浄瑠璃といろんなお祭りや伝統芸能があると思うんですが、そういう文化が北海道には全然なかったので驚いて。サラリーマンの顔をしている一般の人たちも、実は体の半分以上が役者だったり、獅子の使い手だったりする。体の中に、祭りや芸能がある人たちが住んでいる場所だったんですよね。
もちろん日本の他の場所にもそういう地域はあると思うんですけど、自分がそういうものを求めていた時に出会ったのは大きかったです。
後は、いつかは現代サーカスだけで生きていく、ピュアにその仕事をしていきたいと思っていたので、一つの文化を生み出して、国内外からいろんな人を呼ぶという時に、この土地は本当に魅力的だなと思ったんです。
北海道はやっぱり寒さがあって、屋外の活動は一年の半分ぐらいしかできないんですが、瀬戸内海は本当に美しいだけじゃなくて、穏やかで過ごしやすい場所だったので。瀬戸内海の風景と、風土と文化に引かれて移住を決めたという感じですね。
-「大地の芸術祭」という芸術祭の仕事で新潟県も訪れたということですが、新潟県と比べて香川県はいかがでしたか。
新潟県の越後妻有(つまり)、松代という場所にも仕事で1年半住んでいたんですけど、北海道や越後妻有の辺りに比べたら、香川は周りにたくさんの文化圏がある。
高松自体が大きい街ですし、四国のそれぞれの県の他に、岡山とか広島とか関西とか、何なら福岡でもそんなに遠くないじゃないですか。文化に触れようと思えば、素材はいくらでもあるんですよね。
それから、香川には静かな時間というか、自分でしっかりものを考えたり作ったりできる余白みたいなものがある。ものづくりには、こういう余白がすごく必要なんです。
大都市は情報量が多くていろんなことを経験できるんですけど、あまりにも情報が多くて、自分の中から発信してじっくり考えることがなかなか難しいんじゃないかなと思っています。自分はよそにない、世界のどこにもないものを生み出したいと思っていたので、そういうためにはいろんな情報に惑わされている場合じゃないというか…。自分なりの考えを深めていけるところがすごく良かったです。アーティストにとっても、創作活動をするのにすごくいい場所だと思います。
-僕もちょっと気分を入れ替えたい時は、赤灯台の辺りへ夕日を眺めに行きます。景色を見ながら創作の助けにしているような場所はありますか。
確かにサンポートの赤灯台の近辺というか、あの港に行くのはすごく大きいです。あんな場所が近くにあるなんて、世界の中にもほとんどないんじゃないかっていうぐらい、いい場所ですよね。前はあの近くに住んでいたからなおさらだったんですけど、今は離れているので、たまに本当に行きたくなった時は頭の整理がてら歩いていきます。
あそこはちょうど瀬戸大橋が見える方面に日が沈んでいくじゃないですか。あの様子をぼーっと眺めるっていうのは、もう最高ですよね。他にも大好きな場所はいっぱいありますけど、一番疲れた時に行くのってそこかもしれないです。
-高松市に移住後は瀬戸内サーカスファクトリーという団体を立ち上げ、2012(平成24)年に初の本格公演となる「100年サーカス」を上演されました。この公演に至った経緯を教えてください。
私は2011(平成23)年に香川へ移住したんですが、自分が演者ではないので、普及活動というとお話会ぐらいしかできなくて。映像を見てもらいながら定期的にサーカスのお話会を開いていたんです。何だかんだ、その話が面白いと言ってファンになってくれる人はいたんですけど、「やっぱり公演を見せないと分からないだろう」っていうのをすごく感じていたんです。本物の公演を、しかも日本の人と一緒に作る公演をやらなきゃ駄目だと。
フランスの現代サーカスは、普通のテントではほとんどやっていなくて、倉庫の中だったり、いろんなところを使うんです。だから私も「古い倉庫でやりたいな」って、ずっと思っていたんですよね。そうしたら、仏生山温泉(高松市仏生山町)を設計した岡さんから「古い倉庫って、ことでん(高松琴平電気鉄道)の工場とかどうなん?」と言われて…。
「現役で使われている工場は無理じゃないか」と思ったんですけど、岡さんがその場ですぐ、ことでんの今の社長の真鍋康正さんに電話してくれたんです。「田中さんっていう人がこんなことを言ってるんやけど、できるん?」みたいな話をしたら、康正さんはその時点で「面白いね」と言ってくれて。
そこから会社としてOKが出るまでには半年くらいかかったんですけど、やっぱりあの頃はことでんも100周年ということで、ことでんをなるべく身近なものとしてみんなに楽しんでもらえる工夫をずっとされていたので、その中で「サーカスはいいかもね」となったみたいです。
社員さんたちが整備工場として使っている、本当に真剣に働いている場所なので、それをサーカスのために2日間ぐらい空けるのは常識的に考えたら無理だろうって、今だったら思う。ただあの時は、そういう不思議な力が働いて本当にできることになったんです。
最初は何となく反対していた、けげんそうに見ていたつなぎ姿の社員さんたちも、最後の公演の時にはみんな見に来てくれました。何なら手拍子もしながらすごく楽しそうに見てくれて。一体になれたというか、あの時にやっぱり「地元の人と地域で一緒にやるものは、その地域の人にも喜んでもらえる、参加してもらえるものがいいんだ」ということを、身をもって知りました。
単に「場所を貸してください」とだけ言うのは簡単なんですけど、それはイベントが終わった後に、協力してくれた人たちが疲弊してしまったりする。そうじゃなくて、本当にやるなら「一緒にやって良かったし、やった意味があった」って思えないと駄目だなと感じたんです。そういう意味で「100年サーカス」はすごく良かったなと思います。
「100年サーカス」公演の様子
-「100年サーカス」公演を行ってから、何か活動の変化はありましたか。
あの頃の瀬戸内サーカスファクトリーは任意団体で、「イベントがある時には集まるけど、それが終わった瞬間にまた解散」という感じだったんです。継続して活動していなかったせいでイベント屋さんのように思われることも多かった。
実際の活動はそうじゃなくて、地域とともに文化を作るという目的や、地域に活力を生むという意味があるので、「継続的にビジョンを持って成長していくためには、法人化してきちんと運営していかなきゃいけない」と考えるようになって、2014(平成26)年に瀬戸内サーカスファクトリーを法人化しました。
ただここからが苦労の連続っていうか、苦闘の連続っていうか…。公演は半年に1回ぐらい、定期的に大きいものをやっていたんですけど、理事と一緒に年間を通じた運営を考えていくとなった時に、自分は元々会社員、しかも文学部みたいなところの文系だったので、経営面は本当に弱くて。
考え方の順番が違うというか、「認めてもらうためにいいことをやる」じゃなくて、「いいことをやってるんだから認めて」。「地域に貢献するためにいいことをやる」じゃなくて、「いいことをやってるんだから地域に貢献してる」みたいに考えるところがずっとあったんです。でもやっぱり日本の社会、資本社会では経済が大事な部分なので、経済と一緒にやっていけなかったら、日本で文化を作ることは難しいんですよね。
目的は非営利だったとしても、経済的に自立して回していくことができていないと、イベント屋から脱出できない。文化を育てるという本当の目的も絵に描いた餅だったので、そこをきちんとするのが本当に大変でした。
最近の自分の仕事も、半分ぐらいは会社運営みたいな部分が占めています。後の半分で、徐々に徐々にサーカスの作品制作の、中身のクリエーションの質を上げていっている。芸術面でのクオリティーを高めているところです。
最初のうちは、やっぱりある程度素人っぽかったり、ちゃんと作り込まれていなかったりするところが多かったんですけど、いずれは日本の中でも、世界でもきちんと舞台作品として認められるような作品を作って、日本国内、海外でもツアーができるぐらいにしていかなきゃいけないと思っています。
今やっているのは、経済面と芸術面、どちらも年間を通じてきちんと取り組んでいくということ。仕事の質は重くなってくるんですけど、その分周りの評価、全国的な評価も少しずつもらえるようになってきましたし、大変だけど頑張るかいはある、というのが今の状況ですね。
-コロナ禍の今も各地で創作公演を行っていますが、昨年は年間で何回ぐらい公演しましたか。
昨年と一昨年は、秋しかやっていないのにすごい回数をやっているんですよ。コロナ禍になったから逆に前よりオファーが増えたところもあって、以前よりはるかにすごい勢い密度でやったのは確かです。昔は1年に20、30公演くらいだったと思うんですけど、それが昨年の場合は3カ月くらいの間に20公演くらいやっています。
今年は3月までに20公演以上決まっているんですが、やっぱりコロナの影響がすごくあって、来年度はまだあまり動きがない。
昨年、一昨年もそうでしたけど、大体秋に「動けるようになったぞ!」「じゃあもう来年春には行けるね!」と言っていたら、いきなり戻ったじゃないですか。その経験があるから、まだみんな春以降のことを本気で発注できないというか、様子見のところがありますよね。だから頑張れるところまで頑張るしかない。
-最近では「ヌーヴォー・シルク・ジャポン」という企画公演を始め、一昨年は和太鼓と、昨年は能と現代サーカスを融合させたことで話題になりました。この企画の手応えはいかがですか。
能と現代サーカスをコラボレーションさせた「ハナゴロモ」公演の一場面
すごくいいですね。「ヌーヴォー・シルク・ジャポン」という企画では主にJTBさんと組ませてもらっているんですけど、昨年も一昨年も、やっぱり今までと規模感が違うというか。JTBさんが持っているネットワーク、広報力が私のところとは違うので、「観光には興味があるけど、文化にはそんなに興味がない」人にも届くようになりました。
中身に関しても、一昨年はずっと夢見てきた「太鼓芸能集団 鼓童」との共演が企画のおかげで実現しましたし、昨年も玉藻公園(高松市玉藻町)の披雲閣で能と共演するという、これまた自分だったらまだチャレンジしなかったんじゃないかと思うことが、JTBさんのアイデアで実現できました。
この「ヌーヴォー・シルク・ジャポン」という企画はうちの独自企画と違って、「本当に成功させなきゃいけない」というプレッシャーと緊張感がすごい。でもそれが逆に良くて、クオリティーのきちんとしたものを作ろうとする真剣度は半端じゃなかったです。
一昨年、昨年と開催し、結果として今までやってきたものの中で一番いい評価を頂けているんじゃないかな。
ー僕もゲネプロ公演を拝見しましたが、素晴らしかったです。
ありがとうございます。あの場所でみんなで合わせて練習をする時間は限られていたので、ゲネプロの時は様子見な部分もあったんですけど、最終日にはかなり完成したという感じです。能も素晴らしかったですし、古楽も素晴らしかった。そんな人たちと共演できて本当に光栄でした。
うちは劇場じゃなくて、いろんな変わったところでやる公演、いわゆるサイトスペシフィックがめちゃくちゃ多いんです。だから劇場みたいな、真四角の何にもない空間でやる方が逆に怖いですね、今は。
例えば披雲閣での公演だったら、私は披雲閣との対話から入って、披雲閣が語ってくるものを感じ取りながら自分の中でストーリーや妄想を膨らませて、その中でどんなものが立ち現れてくるのかを考えてどんどん実現していくんです。
それってやっぱり場所の力がすごくあって、この企画のために改めて披雲閣に入った時も、「あっ、これはタイムマシンだ!」「この建物自体がタイムマシンになるんだ!」という感覚があったんですよね。
能ではあの世とこの世の世界が描かれますが、一歩足を踏み入れたらそこがもうあの世の世界になっているような、そういうことがああいう空間だとできる。四角くてどこも同じっていう劇場になると、逆にすごく難しいなと思っちゃいますね。
ー確かにそういう場所では、あの幽玄の世界の表現は難しかったかもしれませんね。
披雲閣でサーカスというと、最初から難しいって言う人がほとんどだと思うんです。重要文化財なので重いものは置けないし、天井が高いところもないし。でも、私はそういうところが結構得意なんです。
例えば最後のシーンでは、屋根のひさしの上に人が上がってどんどん見えなくなっていく。実際はあの上って30センチしかないんですけど、そういう風に高さを見せて、あたかも天上界に上がっていくかのようなシーンを作りました。
普通だったら嫌だって思うようなところを逆手に取って人の想像力を膨らませると、もう無限の世界が広がるような感じがあるんです。
-サーカスの公演以外の、現在の活動についてもお聞きかせください。
主なのは、子ども向けのサーカス教室かなと思います。これも昔からやりたくて、何年も準備に時間をかけて、器具も新しく作って2年ぐらい前にスタートさせました。
やっぱりフランスもそうだし、現代サーカスが発展しているところって子どももサーカスをやっている。サーカスが見るだけのものじゃなくて、自分たちもできる、身近に体験できるものなんですよね。だからサーカスっていうものを、それこそ生活の中で感じてもらえるような世界を作りたかったんです。
後は、私は実際にヨーロッパのサーカス教室、サーカス学校を見てきたんですが、子どもたちが本当に楽しんでいるんですよ。子どもにインタビューをしたら、「体操教室は厳しくて駄目だったけど、サーカスなら続くの」なんて答えていました。
要は、やっぱり遊びの要素が楽しいんですよね。もちろん、真剣にたくさん練習することも必要なのですが、競争じゃないし、点数でもないし、自分が得意なものをどんどん伸ばせる楽しさがあるんです。
子どもって高いところに上りたがったり、グラグラしたものに乗りたがったりするじゃないですか。で、大人よりうまいし。サーカスはそういうことの延長線上なんです。
子どもたちは遊びながら体幹が鍛えられたり、運動能力を高められたりする。でも最終的には芸術活動なので個性をすごく重視していて、「こうじゃなきゃ駄目」っていう決まりがない。「それぞれの子どもが発揮するものが一番素晴らしい」という感じなので、普通の子どもでも社交性が出たとか他人に対して優しくなったとか、いいことがたくさんあるんですよ。
サーカスは一人でやるものだけじゃなくて、人の体を支えてあげたり、人の手に自分の体を委ねたりするものがすごくあるので、「この人の安全は自分の手にかかっているんだ」「自分は今この人に支えてもらったんだ」という感覚を得て、結果人に対して優しくなるというか、人の体の強さやもろさも理解するんです。
今の日本の子どもたちは、危ないことを全部止めるように言われるじゃないですか。私が昔自転車に乗っていた時はただ必死にしがみついているだけだったけど、今の子たちはすごくガードされたものに乗っているし、遊具も砂場も、あらゆるものの形が変わってしまっていますよね。「自分の体を支えなきゃいけないんだ」という感覚がどんどん奪われているので、それって危険だなと思うんです。
実際の世の中には危険がいっぱいあるのに、自分の体は自分で守らなきゃいけないことが小さい時に学べなかったら、逆にその子たちの将来に不安を感じてしまう。だから、サーカス教室でそういう経験を積んでもらっています。
栗林山荘(高松市栗林町)でのサーカス教室
-僕も、子どもができたらサーカスを習わせたいなと思いました。
あはは、ぜひ! 結構ハマる子たちも多いですよ。サーカスには天井からぶら下げた布を使うエアリアルティシューというパフォーマンスがあるんですが、あれを低いところでやってもらうんです。
子どもはまず「楽しそう!」って思うんでしょうね。みんなその布を見て「何あれ、ブランコ!?」「乗りたい乗りたい!」。自分の番が終わった後も「まだやりたい、まだやりたい!」って言うんです。
もちろん危ないように先生がちゃんと見ていますけど、チャレンジするのは自分なので、そうやって楽しみながら頑張ろうとするのっていいなと思います。
-瀬戸内サーカスファクトリーは設立から10年が過ぎました。10年後、20年後に実現したいことをお聞かせください。
「文化はみんなで作るもの、みんなで育てるもの」という認識が広まって、当たり前のように地域で文化が行われるようにしたいです。もちろん自然にはできないので、一歩一歩そのアクションをしたいなと思っています。
私はいわゆる劇場のような公的な場所じゃなくても、文化って普通の人たちができることだと思うんです。普通の家の人でも、気持ちとノウハウができてきたら倉庫や庭で1週間アーティストを受け入れて、そこで作品を作ってもらうとか、コラボレーションをするだとか。地域が丸ごと作品創作の拠点になっていくような世界ですね。
やっぱり瀬戸内って風景もいいし、例えばどこか遠い国の人がインターネットで「ここにはこんな滞在制作をさせてくれる場所があるんだよ」「こんな場所で公演ができるんだよ」って言ったら、「行きたい、行きたい!」って来る人は絶対にたくさんいる。
だから生活の中で普通にそういう人、そういうものを受け入れて、一緒に文化を作っていく仲間が増えていくといいなと思っています。それが引いては、生活の支え合いにもなるんじゃないでしょうか。
多分この先、日本の文化予算がオリンピック前後よりも増えることはまずないと思うんです。いろんな予算が減っていった時に、今のままそういうものに頼っていると、日本の文化は本当に消えていってしまう気がするんですよ。
その危機感があるから「文化って普通にできるんだ」「関わっていいし、どんな形でもあり得るんだ」っていう世界を作っていきたい。そのために今は鉄工所であったり飲食店であったり教育機関であったり、いろんな所へ行って仲間を作っています。
文化は、人の心に絶対に必要なもの。昔から人間は「農作物がちゃんと実りますように」とか、「災害が来ませんように」とか、祈りを込めていろいろなお祭りをやってきたわけじゃないですか。その中に芸能があって、だから芸能って本当に古来人間の生活と結び付いていたはずなんですよね。
戦後の日本は資本主義社会、経済優先の社会にガラッと変わって、そこで文化活動というものが、私たちの生活にはほとんどないものになってしまった。でも人間、経済だけでは生きていけないから、文化を守るためには、普通の一般の人たちが文化の主体になるのが一番いいと思っているんです。
-田中さんは現代サーカスという未知の世界に飛び込んでいきましたが、今、世の中にはチャレンジしたいけれど、なかなか一歩踏み出せない人も多いと思います。そういった方へのメッセージと、高松経済新聞へのメッセージを頂けますか。
昔、自分自身が本当にそういうタイプだったんですよ。怖がりで、小さいこともできない人間でした。留学をした時はその怖がりがマックスで、臆病で何もできなかったことがすごくトラウマになっていたんです。
それからちょうど10年ぐらいたった時に、サーカスの人たちに出会いました。この時に「明日生きているのは、この体一本があるということに過ぎないんだ」って気が付いたんですよね。
どんなにお金があろうと、結局この体がなくなったら、死んでしまったら終わりじゃないですか。みんな大きく考え過ぎていて、人間っていう一本の体であることを忘れてしまうんですけど、「この体があれば明日も生きているんだ」ってシンプルに考えると、いろんなチャレンジも怖くなくなるというか、案外何でもできるんだなって思える。自分の転換点は本当にそこで、それまでのいろんなモヤモヤや怖さが吹き飛んでしまいました。
「多分これぐらいの食べ物と水があったら、明日も私、いるな」「それぐらいのものだったら、どんなに仕事がなくても稼げるだろう」「何とかなるだろう」って思ったんです。だからチャレンジを恐れないで、自分の体の分量をシンプルに考えたら、明日も頑張れると思います。
いろんな人が言われたことかもしれませんけど、やっぱりこの香川、高松という場所はすごい。例えば自分だったら、「全てを捨ててここに来てもいい」と思ったぐらいの場所ですし、この場所の魅力、持っているものは計り知れないと思うんです。でも、地域の人はそれほどそれを感じていないと感じることがあまりにも多い。
だから高松経済新聞さんは、地域の人が気付いていない魅力を発信して、さらにいいものにしたいと思っていらっしゃるんだろうなと思います。地域に仲間ができたなと感じていますので、これからもよろしくお願いします。
取材を行ったのは昨年12月。香川での「ハナゴロモ」公演と、北海道での「サーカス・イズ・アート」公演が終わった直後のことでした。
数々の活躍から熱量のあふれる方を想像していましたが、画面越しに出会ったのは穏やかな、どこか少女のような無垢(むく)な瞳。後から思えば、あの瞳は田中さんが衝撃を受けたというサーカスアーティストたちの真っすぐな目と同じものだったのかもしれません。
多忙を極める中、取材へのご協力ありがとうございました。高松経済新聞は今後も高松を元気にするような方々と、その取り組みを取り上げていきます。
次回の更新もお楽しみに!