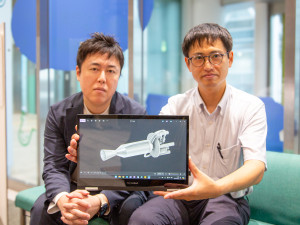高松・歯ART美術館で西公美さん個展 庵治石の石粉使う陶芸「炉器」並ぶ

庵治石の石粉を混ぜた粘土で器を作る西公美さんによる個展「つちとわたし、いしとわたし」展が現在、高松・歯ART美術館(高松市庵治町生ノ国)で開かれている。
三重県出身で現在は三木町で陶芸とベンガラ染めの教室「アートスペースにしくみ」を開く西さん。昨年6月から庵治石の石粉を混合した「あじ粘土」を使った食器「Loci(ロキ)」を作り始め、昨年度の香川県産品コンクールで最優秀賞も受賞した。西さんは「香川に移り住んでから庵治石のことを知り、石材店の方とも知り合いになった。話す中で庵治石の加工の時に出る石粉を産業廃棄物として処分していることを知り、何か有効に活用する方法はないかと考えるようになった」と振り返る。
最初はうわぐすりに混ぜて作っていたが、粘土に混ぜればもっと石粉を大量に使えるのではないか考えあじ粘土を作ったという。粘土には庵治石の石粉を50%以上配合しており、軽くて強度もある。半分土で半分石を使っているので土から作る陶器でもなく石から作る磁器でもない「炉器(Loci)」と名付けた。「Loci」はラテン語で「土地の神」を指す言葉、西さんは「香川の大地から生まれた庵治石を使った器なのでそれもかけている」と話す。
展示ではLociのコップや皿、動物をモチーフにした食器や石を模して作った花器、波や光をモチーフに描いた「あじ粘土」の陶板など約50点のほか、庵治石の石粉を混ぜたうわぐすりのテストで制作した小皿300枚が並ぶ。西さんは「花器は大地から生まれた物で作った器をあえて石の姿に似せたら面白いと石の形にデザインした。現実に起こるはずのないことを例える言葉に『石に花』も意識している。陶芸の前は油絵を描いていたので絵画みたいな作品をと思い陶板の作品を制作した。これまで表現してきたことの集大成のような展示」と話す。
テストで作った小皿については「商品として並んでいる器も完成までには試行錯誤がある。自分が並べたのは300枚だが、著名な作家だと数千、数万点は試作していると思われる。そんな陶芸の裏側も知ってもらいたいと展示した」とも。
3月30日まで。
同美術館の開館時間は10時~17時。入館料は、大人=600円、中学・高校生=300円、小学生以下無料。