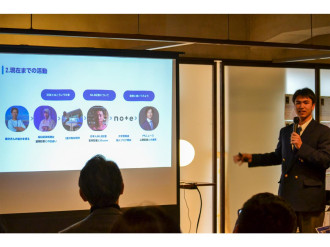かもねのたかまつ歴史小話(7) 戦国時代の讃岐の栄枯盛衰 part.5
かもねのたかまつ歴史小話(7) 戦国時代の讃岐の栄枯盛衰 part.5
【香西氏と十河氏の春日川をめぐる攻防「高松平野を支配せよ!」】
前回、三好氏が讃岐において覇権を握る話をしたが、今回はそこから時を戻して再び高松に焦点をしぼり、香西氏と十河氏の騒乱を見ていくこととする。
香西氏について:https://takamatsu.keizai.biz/column/21/
十河氏について:https://takamatsu.keizai.biz/column/22/
讃岐の戦国時代を応仁の乱から豊臣の四国征伐までとすれば、その期間のほとんどは高松の場合、香西氏と十河氏・三好との抗争だった。よく言われる長曾我部元親の侵略は100年近く続いた戦国時代のうちの末期の5~6年の話でしかない。
今まで讃岐の歴史家は戦国時代といえばこの5~6年程度の長曾我部元親との戦いのみを強調して語ってきた。そのために長曾我部が来るまでの100年近くあった讃岐の戦国時代についての研究は進まず、評価されるべき多くの武将や豪族の名が隠れてしまっている。
今回は高松に絞り込んで戦国時代の様子を簡潔に説明したい。
1. 香西氏の支配域
江戸時代の始まりまでの高松は香東川から流れる砂だまりによって形作られた洲であった。古くは「八輪島」と呼ばれ、野原郷が存在した。高松城跡がほぼその先端と考えられている。そこから東を見渡せば対岸に屋島が見える。ここから現在の今里町付近まで遠浅の海岸だったと識者は語る。

野原郷には野原港があった。この港は石清尾山隗の南東に位置した坂田郷(現在の西ハゼ町の辺り)や陸地奥の円座や陶、中間との荷運びを、香東川を通じて行うための拠点施設だった。
それらの地は皇族や上級貴族の所領の地であり、安全確実に都との流通を行わなければならなかった。
この要衝の港を守る役割として有力国人の香西氏の管理が必要不可欠だった。
野原郷は香西氏配下の岡田氏、雑賀氏などが館を築いて支配していた。
香西氏の支配域は現在の香西町辺りのみならず、この野原から高松東部は牟礼、南部は現在のサンメッセ香川(高松市林町)、西部は綾川町までと広大だったと考えられる。
つまりは高松平野のほとんどは香西氏の支配下にあったと考えればいい。
(関連記事:https://takamatsu.keizai.biz/column/17/)
2. 十河氏の支配域
香西氏が支配する高松平野であるが、その東を流れる春日川・新川流域は十河氏の支配下となっていた。細川政権の頃に春日川の河口にあたる屋島の麓に「方本(かたもと)」という港が造られ、その管理を十河氏が任されていた。
香西氏の野原港が坂田などの皇族・貴族への物流を目的としていた港だったのに対して、こちらの十河氏管理下の方本港は塩や穀物などの特産物を都に送るのが主な目的だったと思われる。方本は「潟元」の地名として琴電志度線の駅名として現存している。
 潟元駅
潟元駅
十河氏は王佐山城(上佐山城とも)と十河城を本拠地として、春日川と新川伝いに本州との交易や補給を行っていた。方本港はその中継のための港だった。この補給・交易ルートを遮断されると十河氏は困窮する。この視点で当時の香西氏と十河氏の配下の配置(布陣)を見てみよう。
 屋島山上から見た香西氏と十河氏の勢力図
屋島山上から見た香西氏と十河氏の勢力図
3. 春日川流域における香西氏と十河氏の争乱
1500年代初期~1570年代初頭、香西氏と十河氏は高松において激しく勢力争いをした。
香西陣営は春日川・新川の十河氏の補給・交易ルートの遮断を狙って喜岡城(旧高松城)と向城に、それぞれ高松氏と真部氏を置いている。喜岡城は相引川対岸に方本港が見え、新川からも遠くない。向城は春日川河口に位置して、こちらも対岸に方本港を望む。
この2つの城は明らかに方本港から王佐山城と十河城への補給線を監視または阻害する目的があったことが見て取れる。
もちろん十河氏側もこれを看過していない。新川の河口近くの久米山付近(現在の前田)を腹心の前田氏に抑えさせて喜岡城と向城をけん制させると共に、向城に隣接して木太城を造り、一族の神内(じんない)氏を配した。この向城と木太城は完全に隣接した位置にある。向城は先述の前田氏(甚之丞)の夜襲に遭って女子どもともに殺りくされたために真部氏は滅んだと四国の中世史について著す「南海治乱記」(香西成資著)は語る。

 現在の前田城跡
現在の前田城跡
春日川をさかのぼれば由良山がある。讃岐平野によく見られるオニギリ山だ。
 由良山
由良山
昭和の中頃までは皇居にも使われる高級石材の採石場だった。この山には「由良山城」があり、十河氏一族の由良氏が守っていたとされる。その位置から、この城も春日川の水運を監視する役割を持っていたと考えられる。要衝の地であり、香西氏は総力を挙げて、この城を何度も攻めており、落城したとも、降伏したともいわれる。
この城の脇を流れる春日川をさらに上流へ向かえば王佐山城にたどり着く。十河氏一族の三谷氏が守るこの城は香西氏のみならず東讃の寒川氏も何度となく攻めているが落城には至っていない。
 大宮八幡宮から見た王佐山、由良山、久米山
大宮八幡宮から見た王佐山、由良山、久米山
香西氏は王佐山城と由良山城の攻略を視野に入れて双方の城を監視できる多肥(現在のサンメッセ付近)に高木城を築いた。もっとも城主として置いた乃生(のう)氏は調略によって十河氏へと寝返ったために香西氏に討たれている。両勢力の高松での小競り合いは、このように春日川域を中心として起きている。
 乃生(のう)氏を祭った多肥の「乃生大明神」
乃生(のう)氏を祭った多肥の「乃生大明神」
筆者の私見では十河氏支配下への香西氏の侵攻が頻繁なので一定の時期までは香西氏勢力の方が、やや優勢だったのではないかと思われるが、互いに決め手もなく拮抗(きっこう)した争いだった。
ところがこの拮抗(きっこう)は三好氏と十河氏の血縁関係が築かれるに至ってついに崩れた。強力な三好氏の支援を得た十河氏はそれまで敵対していた高松の香西氏、多度津の香川氏、東讃の寒川氏らを一気に服従させて讃岐全土を支配下に置いてしまったのである。これは讃岐が十河氏の元に統一されたというよりも、十河氏を介した三好氏によって旧細川政権の足元たる讃岐を奪われたともいえる。
このコラムでは知るとちょっと奥深い高松の歴史について紹介していきます。
どんな「歴史小話」が飛び出すか、次回もお楽しみに。
「かもね」ツイッターでも日頃の取材や歴史の情報を発信しています。
https://twitter.com/setoumibutyo